講義余話
瑞穂の国の風景
いきなり私事の話になって恐縮だが、最初に子供ができた時、男子ならば「瑞彦(ミズヒコ)」と名付けようと思い、そうした。
「彦」は、「海幸彦」「山幸彦」の「彦」で、古代からある日本男子の伝統的な名を構成する大和言葉である。つまり、個別の語彙を前に置いて「○○ヒコ」と作るのである。「ヒコ」は、概念としては「日子」である。すなわち、“太陽の子”という意味であり、同様の概念としては、「日女(ヒメ)」(「媛」「姫」と表記された)があるが、これは女性の場合である。
そして、「ヒコ」の前に置いたもう一つの構成要素の「瑞(ミズ)」は、「瑞穂(ミズホ)」から取った。この言葉も大和言葉と考えていい。「ミズ」は、「みずみずしい」という意味を持つ形容詞として、今日の現代日本語にも使われるが、漢字の「瑞」は当て字かもしれない。大和言葉としては、むしろ「水(ミズ)」からくる清新な美しさを言うのであろう。まさにみずみずしい美しさを言う言葉なのである。「穂」は、もちろん「稲穂」である。
「瑞穂」とは、私のイメージとしては、故郷の田園風景の清新で青々とした緑の絨毯のイメージがある。風が吹くと、その絨毯は、あたかも魔法が掛かったかのようにいっせいに波打ち、見事なハーモニーを形象した。その世界は、あくまで私のふるさとの夏の風景であり、さらに、今となっては、失われた心の原風景と言っていい。
まだ郷里に住んでいた頃―高校の頃だったと思うが、夏の日の早朝、田圃の周縁を歩いていると、その緑の絨毯が、まるで生き物がかすかに目覚めたかのように、いつもより微妙に明るい表情になっていることに気づいた。近づいて目を凝らすと、小さな「稲穂」が、一斉に顔をのぞかせていたのである。“穂立ち”であった。青々とした緑の田園が、ひと際明るく生き返ったかのような印象であった。
だから、「瑞穂(ミズホ)」の「ミズ」とは、おそらく穂立ちの「みずみずしさ」を言ったものに相違ないが、しかし、私にとって「瑞穂」という言葉からもたらされる世界は、あくまでも、この国の夏の田園風景の風に波打つ緑の絨毯であって、その一面の光景が今もゆたかな優しさとともに、脳裏に蘇る。ただし、わがふるさとの田園の緑は、国の減反政策で、荒れ果てた。

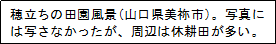
言うまでもないことだが、我が国の“租税”は、基本的に「稲穂」であった。全国から中央政府に集められた租税の「稲穂」を、古代律令国家は、そのまま「稲束」にして貴族に配給した。だから、「租税」も「給料」も、つまりは、「稲」ということであった。そもそも「禾偏(ノギヘン)」じたいが「稲」のことであるから、稲の収穫の季節である「秋」も禾偏から成るのである。
税と給料とが「稲」(後には「米」)であったのは、基本的に江戸時代まで続くことになった。たとえば、“加賀百万石”などと言う大名の経済規模や「五十石取り」とか言う江戸時代の武士の俸禄(扶持米)を言う場合などの「石」とは、いずれも「米」の容量を表す言葉であったことは言うまでもない。
従って、稲作農耕社会が、この国の基本的な“かたち”であり、その意味では、この国の起こりに“弥生文化”(稲作農耕文化)を据えることは間違いではない。その文化の源流は、おそらくは、多くが朝鮮半島からもたらされたものと思われるが、その中核として勢力を拡大していったのが、いわゆる「大和朝廷」を形成した人々であった。そして、その求心力となったのが「天皇家」であった。
そのため、天皇の祭祀として、毎年秋に稲の収穫を神に報謝する行事、「新嘗祭」(にいなめさい)が執り行われている。しかし、戦後、この日の祝日名は変更され、「勤労感謝の日」という、なにやらわかりにくい祝日となった。天皇が主宰する祭日から国民の祝日への転換ということであろうが、すでにこの国は、稲作農耕の国ではないという意識の表れでもあったと言える。
ところで、延喜5年(905)年に成立した勅撰和歌集である『古今和歌集』は、きわめて深い意味を持つ“歌集”なのだが、それを一言で言うならば、「天皇の歌集」ということであろう。天皇とは醍醐天皇であり、この時代は安定した治世で、二代後の村上天皇時代までを含め“延喜天暦の治”と称えられた。政治が安定するということは、経済が安定するということであり、"民の竈(かまど)"から煙が昇り続けることは、天皇の責務でもあったのである。
つまりは、『古今和歌集』の「四季」の“部立”は、醍醐天皇の治世の正しさを表象するもので、穏やかな自然の推移と維持もまた、天皇の有する力の成果でもあったのである。そう言えば、藤原定家撰の「小倉百人一首」の冒頭が、この国の中央集権国家の土台を作った天智天皇(668~671在位)の歌であった。
秋の田の かりほのいほの とまをあらみ わが衣手は 露にぬれつつ
長谷川哲夫氏の『百人一首私注』(風間書房、2015.3.31)によれば、定家は、「かりほのいほ」を“刈穂で葺いた粗末な宮殿”と解していたようだが、そうだとしたら、いかにも「瑞穂の国」の王にふさわしい住居と言えるのではないか。
かつて、夏から秋に向けての豊穣なる瑞穂の田園風景は、この国の為政者の理想であった。まさに「瑞穂の国」とは、言い得て妙ではあるが、国際化時代、今に残るこの風景でさえ、今後守り続けていくのは、やはり容易なことではない。


