講義余話
行平の須磨
「汐汲」と「松風」
歌舞伎舞踊に「汐汲」という演目がある。その踊りは、文字どおり「汐」を汲む所作の踊りなのだが、その時の衣装がおもしろい。烏帽子(えぼし)に狩衣(かりぎぬ)姿なのである。「海女」が王朝貴族の衣装をそのまま身にまとい汐を汲むというのであるから、リアルに考えると、なんだか常軌を逸しているようにも思われる。
源融の河原院以降、貴族文化が“鄙”の風景を積極的に取り込むことが行われるようにもなり、あるいは、そういう雅(みやび)と鄙(ひな)との融合という王朝の美意識の顕現と捉えられるのかもわからないが、ともかく、“鄙”の風景である「汐汲み」に、王朝貴族の「烏帽子」と「狩衣」というアンバランスな組み合わせが、この舞踊の見物と言っていいだろう。
ことの発端は在原行平(818-893)である。行平は在原業平の兄で、父は平城天皇の子の阿保親王だが、母方の家は知られていない(業平の母は伊都内親王)。行平の生涯は、業平とは違って、比較的順調に昇進したかに見えるが、『古今集』(905年)によると、文徳天皇時代(850-858)、一時須磨に籠居したことがあった。そのことは、『古今集』に、次のように記されている。
田村の御時に、事にあたりて、津の国の須磨といふ所にこもり侍りけるに、宮のうちに侍りける人につかはしける在原行平朝臣
わくらばに 問ふ人あらば 須磨の浦に 藻塩たれつつ わぶと答へよ(文徳天皇の御代に、あることに関わって、摂津の国の須磨というところに籠りました時に、宮中に仕えていた人に詠んで送ったうた)
(たまに、自分のことを、どうしているかと尋ねる人がいたならば、行平は須磨の浦で、藻塩が垂れるように毎日泣き暮らし、つらい思いで暮らしているとお答えください。)
この『古今集』のうたと詞書とからすると、行平は、「田村の御時」に「事にあたり」、その結果、しばらく須磨に籠もった、ということになる。このことについての詳細は不明とされているが、ただ、行平と須磨との関係については、『伊勢物語』「87段」でも語られており、そこには、例の業平が絡んでいる。この行平の須磨籠居の問題については、業平に関わりがあると考えるとおもしろいが、このことについては、いずれ触れなければなるまい。
さて、行平のことである。行平は、須磨での暮らしで二人の女性(姉妹)を愛したという話が伝わっている。この話を、後に、世阿弥が能楽の「松風」に仕立て上げたものと思われるが、現在須磨にある「松風村雨観音堂」は、行平の謫居跡に彼を慕う姉妹が結んだ庵の跡と言う。そして、そこには、行平が須磨を離れる際、形見の烏帽子と狩衣とを掛け置いたという「松」の古株が残っている。あるいは、この「烏帽子」と「狩衣」を遺したという話自体、能の「松風」からの連想なのかもわからない。

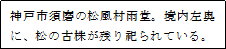
能の「松風」は、旅の僧が二人の女(松風と村雨)の霊に遭遇し、その菩提を弔うという話なのだが、これがやがて、歌舞伎舞踊に受け継がれたのである。ちなみに、能の「松風」に登場する二人の娘の名は、「松風」「村雨」と言うが、その姉妹の墓が、須磨の海岸からやや奥まったところにある。

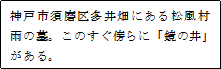
須磨観光協会の解説によると、「松風」「村雨」という姉妹の本名は、「もしほ」と「こふじ」であったらしい。いかにも鄙びた名ではあるが、土地の村長(むらおさ)の娘であったといい、それに行平が、典雅な名を与えたという。また、墓の近くには、「鏡の井」という井戸が残るが、「松風」と「村雨」の姉妹は、行平と逢うときにはその井戸の水面に姿を映したというから、これは、いかにも、須磨という“鄙”にふさわしい逸話には違いない。いわゆる“姿見”ということで、本来、室内で行うものであり、化粧もまた、室内にある“鏡”を用いるものであることは言うまでもない。
つまり、この姉妹の日常は、海女としての“汐汲み”の仕事だったのである。それを、行平から「召(め)し」があった時には、この井戸で、身体の汐臭さをすすいで化粧を施し、夜の「伽(とぎ)」に上がったものと思われる。
能の「松風」は、この行平の須磨での話に基づいていると思われるので、シテの「松風」、ツレの「村雨」と、二人の姉妹が登場するのは当然のことであるが、しかし、歌舞伎舞踊の「汐汲」は、基本的に踊り手が一人であって、この踊り手の装束が「烏帽子」と「狩衣」なのである。
これは、歌舞伎舞踊において、単に「烏帽子」と「狩衣」とを一人の人物にまとわせただけのことかもわからないが、しかし、二人から一人という流れには、行平がいなくなった後の“時”の経過とともに、姉妹の行平への思慕が妄執となり、やがて、狂気にも似た凄まじい女の情念へと昇華していった過程を思わせるものがある。
その狂おしくも美しく燃えさかる女の情念が、ついには、“汐汲み”という“海女”の日常の行為を、妖しく変貌させていったのではなかったか。
ところで、冒頭、“汐汲み”という行為と王朝貴族の「烏帽子」と「狩衣」との組み合わせについて、常軌を逸しているようにも思われる、との印象を述べたのは、もともと、この行平の伝承話が、ある種の本質的な“異常さ”を持っていることに起因しているのではないかと思われる。
この伝承話の“異常さ”と言えば、何と言っても、行平が愛した女が“姉妹”であったということだろう。厳密に言えば、村長が自分の二人の娘を行平に差し出したという構図なのだが、実はこの構図には、日本文学文化史上、ある重大な意味が隠されている。
その真相を探ってゆかねばならないが、あるいは、それは、古代日本人の魂のようなものに触れる作業かもわからない。


