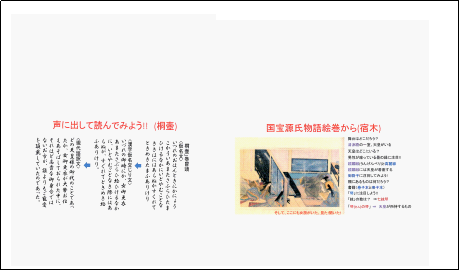講義余話
「源氏物語を楽しむ会」報告と感謝の言葉~第18回ホームカミングデー~
第18回東洋大学ホームカミングデー(11月8日)での「源氏物語を楽しむ会」は、本部企画としての実施ではあったが、会場となった6204教室は、懐かしい顔も多く見られた。来場者は百名近くに上り、用意された資料が大幅に不足するといううれしい悲鳴も上がって、王朝文学文化研究会のメンバーが、急遽増刷に向かってくれた(アリガトウゴザイマシタ)。
前半は、「音読の楽しみ」と題して、「桐壺」と「若紫」の場面を来場者と一緒に音読してみた。
『源氏物語』が制作された時代の、物語を読む“行為”は、「黙読」より「音読」が普通だったと思われる。『源氏物語』の「螢」巻では、女房が実際に物語を読む現場について光源氏が言及しているし、「国宝源氏物語絵巻」の「東屋」の場面では、女房が物語を読んで聞かせている場面が描かれてもいる。
この絵巻の場面、物語を楽しんでいる姫君は“浮舟”で、異母姉にあたる中の君が住む邸(二条院)に身を寄せているところであった。中流の受領層に育った“浮舟”は、「物語絵」は初めての体験であったはずで、彼女はひたすら「物語絵」に見入っているのである。彼女は「絵」を見ながら「物語」を聞いているのだが、そのような楽しみ方が、最上流の貴族の姫君の物語享受のあり方であった。
つまり、姫君は、女房の“語り”によって物語を聞いて楽しむのである。さらに言えば、『源氏物語』は、もともとそういうもの(老女房の回想と語り)として制作されているわけであって、別の言い方をすれば、本文である「物語」は“音読用のテキスト”でもあったのである。
そして、その“音読用のテキスト”は、女性たち(女房)が読むものであり、基本的に「仮名書き」であった。そこで、当日配布したテキスト資料の「桐壺」巻、「若紫」巻の本文は、すべて仮名書き表記とし、当時の“仮名を読む”行為を再現すべく全員で声を出して音読したのである。
漢字も濁点も句読点もない“仮名書き源氏”を読んでいくと、不思議なことに、いたって読みにくい。すらすら読みにくいから、当然のことだが、丁寧かつスローモーに読んでしまう。あるいは、これが、当時の“音読”のスピードだったかも知れないということで、しばし、王朝貴族文化の雰囲気を楽しめたように思う。
後半は、「絵巻で楽しむ源氏物語」として、「国宝源氏物語絵巻」の模写版をスライドに写しながら、その解説を行った。まず、「東屋」巻の場面は、「宇治十帖」の浮舟が「物語絵」に夢中になっているもので、まさに、女房が「声」を出して“音読”しているものである。『源氏物語』の場合も、間違いなく「物語本文」と「絵」があったはずだ。そういう時代の鮮やかな記憶として、この「東屋」の場面はあるように思われる。
また、「宿木」巻の「清涼殿」室内に於いて、天皇と薫とが囲碁を打つ場面では、その室内に置かれるすべての調度類が、当時の時代考証として、極めて正確であることに驚かされる。
そもそも「国宝源氏物語絵巻」の成立は、ほぼ平安末期と思われるが、貴族文化そのものが保守的であり、前代のものをそのまま引き継いでいると判断していい。そのいい例が、たとえば、当日、焦点を当ててみた「畳の縁(へり)」と「琴」である。
「宿木」巻の場面は、構成上大きく二分割されているが、画面右側に男性が二名配置されている。一人が天皇で、もう一人が薫大将なのだが、身につけている衣装などではよくわからない。しかし、着座の「畳」が違うのである。一人は「繧繝縁(うんげんべり)」の畳に座り、もう一人は、「高麗縁(こうらいべり)」の畳に座っていることがわかる。
平安時代の建物の床は、基本的に板敷であった。今で言う「板の間」である。当時の富裕層(最上流貴族)は、この板敷に「畳」を敷いたのである。全体に渡って敷く場合もあったが、基本的には、貴人が座る辺りに敷けばよかった。時には、その畳を重ねて敷き詰め、高い場所を「御帳台(みちょうだい)」としても使用した。
その畳の縁が、天皇やそれに準ずる貴人の場合、「繧繝縁」であったのである。「源氏物語絵巻」では、つまり、着座の畳の縁で描かれている人物がすぐにわかるのである。
また、この「宿木」の場面、清涼殿の室内には「御厨子」があり、その最上部に「琴」が置かれているのが分かる。一部の解説書では「箏の琴」としているが、丁寧に「絃」の数を数えると、その数は“七本”であり、十三本の絃の「箏」でないことは明白である。すなわち、これは「七絃の琴」=「琴(きん)の琴」なのである。
普通「琴(キン)」と呼ばれる「七絃の琴」は、古代、中国から移入された。中国では、「君子」の持つものとされ特別視されたが、日本では、むろん「天皇」、および、それに準ずる高貴な人物が保持するものとなった。
そういう「琴(きん)の琴」の特性をうまく利用したのが『源氏物語』である。つまり、“天皇の内実”を持つ光源氏は、この「琴(きん)の琴」の名手であり、保持者であるという設定である。たとえば、「若紫」巻の北山の場面では、僧都との別れにおいて、「優曇華の花」に准えられる源氏が「琴(きん)」を演奏するくだりが用意され、まさにその“聖性”を裏付けるものとして印象的であるし、さらに、後の須磨流離の際に、この「琴(きん)の琴」を確かに身に付けて下るのも、光源氏の“内実の聖性”を示すもの以外の何ものでもなかろう。
以上、ホームカミングデーでは、『源氏物語』を、常に“文化”の次元において理解してゆくという普段の私の実践の一端について、披露させていただいた。
【当日の配布資料の一部】