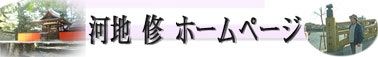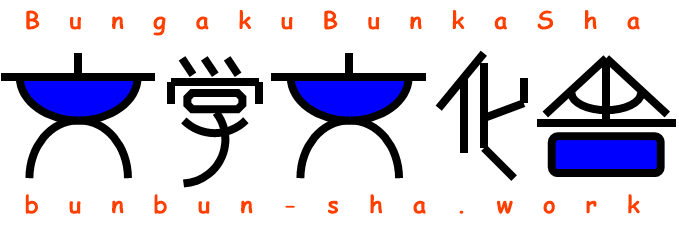-伊勢物語論のための草稿的ノート-
第113回
「いにしへのにほひはいづら」(62段)(一)
「62段」と「60段」の相似性
62段は、前段の61段、60段と並列的に配置されている。物語の舞台はいずれも「人の国」(地方)ということで共通しており、さらに、内容的には、60段が示すところのテーマと一致している。そのテーマとは、元の「男」の「通ひ」が間遠になったことで、新しい男の誘いに従って地方へ下り、そのことから「運命が暗転した女」の物語と言っていい。次に本文を掲げよう。
昔、年ごろおとづれざりける女、心かしこくやあらざりけむ、はかなき人の言につきて、人の国なりける人に使はれて、もと見し人の前にいで来て物食はせなどしけり。夜さり、
「このありつる人たまへ」
とあるじに言ひければ、おこせたりけり。男、
「我をば知らずや」
とて、
「いにしへのにほひはいづら桜花こけるからともなりにけるかな」
と言ふを、いとはづかしと思ひていらへもせでゐたるを、
「などいらへもせぬ」
と言へば、
「涙のこぼるるに目も見えず。物もいはれず」
と言ふ。
「これやこの我にあふみをのがれつつ年月ふれどまさりがほなき」
と言ひて、衣ぬぎて取らせけれど、捨てて逃げにけり。いづちいぬらむとも知らず。
(昔、数年男が通って来なかった女は、しっかりした考えがなかったのであろうか、いい加減な甘い言葉に乗せられて、地方に住んでいる人に使われる身となって、元の夫の前に出て行って食事の世話などをしたのだった。夜になって、元の夫が、
「この先ほどの女を夜伽に下され」
と、主人に言ったので、女を寄こしたのだった。元の夫である男は、
「自分のことを知らないのか」
と言って、
「昔のあの魅力的な美しさは、いったいどこに行ったのだ、美しい桜の花がみな散ってしまい、あるのは汚い幹だけのようなお前であることだ」
と男が言うので、女は、たいそう恥ずかしいと思って何も答えないでいたところ、男は、
「どうして返事をしないのか」
と言うと、
「涙がこぼれるので、目も見えない、ものも言われない」
と、女は言う。男は、
「これがまあなんと、お前のすがたなのか、私のもとから妻であることを逃れ去って、年月が経過したが、まったく幸せにはなっていないことよ」
と言って、夜伽の報酬として衣を脱いで取らせたが、女は棄てて逃げてしまった。どこへ行ってしまったのだろうかわからない。)
述べたとおり、62段は、61段を挟んではいるが、既出の60段と物語の構造が似ている。60段の女は、その夫が「宮仕へいそがしく、心もまめならざりける」ということで、別の男からの求婚を承諾、62段の女は、男が「年ごろおとづれざりける」ことから別の男の甘い誘いに乗った。60段の女は騙されたわけではなく、62段の女は騙された、という違いはあるものの、両者の物語構造は同一であろう。「相似」という言葉を用いる所以である。
ただ、61段も含むが、三章段とも物語の舞台を「人の国」(地方)とすることが共通している。つまり、地方に下った女、というところに、三章段共通のモチーフがあるように思われる。そもそも「物語」という、王朝貴族社会の女性を読者の対象とした娯楽媒体において、その舞台を都以外の土地、すなわち地方とすることは珍しい。貴族社会の女性が地方に下るのは、それなりの理由がなければならないのであって、そういった物語に貴族社会の女性が親しむのは、その女性たちもまた、そういう事態になりやすい環境に生きていることを示している。
60、62段は、主人公の「女」が、いずれも元の男を不誠実と判断し、新しい男と地方に下るという点に共通の特色がある。夫婦として生活している男女のうち、女が、夫である元の男の態度を不誠実と判断、夫婦生活に見切りをつけて、別の男と夫婦になろうとする話は、既出の24段にも見られる話である。単純に考えれば、女の浅慮を非難するかの印象があるが、ここには、当時の中下流階層に生きる女たちの厳しい現実があるように思われる。
「婿取り婚」から排除される女たち
当時の貴族社会が、おおよそ「上・中・下」の三階層に分かれることは、『源氏物語』「帚木」巻の「雨夜の品定め」にも詳しい。中宮彰子を第一の読者とする『源氏物語』が、受領層に相当する「中の品」(中流階層)について詳細に解説するのは、「上の品」の光源氏と受領層の空蟬、夕顔との恋物語展開の伏線的前提でもあったが、同時に中宮彰子への教育的配慮ということもあったに違いない。中宮となった若い彰子に向けて、こういう世界に生きる人々も知ってほしいという作者なりの思いがあったとも考えられる。
『伊勢物語』の場合、その第一の読者は、作者が所属するところの受領層の女たちと言っていい。紀貫之作者説の立場から言えば、それは、紀氏一族の女たちであろう。『土佐日記』を読んでもわかるように、男たちが、赴任する任国へ国司の一員として下る場合、妻たちはそれぞれの夫に従うことが多かった。夫婦で下るわけだから、帰るときには、子供が増えている場合もあったのである。
しかし、『伊勢物語』の60段や62段のケースは、そういう男女(夫婦)の関係ではないように思われる。婚姻関係としては、緩い関係のように思われるのである。つまり、男が、親の庇護のもとで生活する女に「婿」として通う、といったような正式な婚姻のかたちではないのではあるまいか。女が、親の住む家とは別の場所に住むか、あるいは、女を庇護する親がいなくなった家に住み、そこに男が通う、というような、自由度の高い、別の言い方をすれば、かなり不安定な男と女の関係なのではないかと思われる。
ここに言う、「親の住む家とは別の場所に住む」、あるいは「女を庇護する親がいなくなった家」とは、どういうことか。
この時代の貴族階層の場合、その婚姻形態は、基本的に、いわゆる「通ひ婚」(婿取り婚)であった。夫となる男が、その家の娘に「婿」として通い、若いうちはその家で世話を受けるのである。子が生まれると、子は男女に限らずそのままその家で養育され、そのなかで、成長した娘(長女の場合が多い)が、自身の母と同様に、やがて婿を迎え入れてゆくという形態(母系制)である。
しかし、この母系制は、娘の庇護に当たる親が亡くなった場合、状況によっては、極めて深刻な経済的危機に陥った。たとえば『源氏物語』「若紫」巻での紫の上の物語は、まさに、そういった危機に直面しているヒロイン(紫の上)を、偶然北山で発見した光源氏が救い出すという、ある種「お伽話」としての物語でもあった。
また、中下流階層では、庇護する親がいたとしても、すべての姉妹に「婿」を迎えることは難しかった。親の経済的な事情から、それを許さなかったのである。
裕福な「上の品」の階層の場合は、複数の姉妹がいても問題はなかったであろう。それぞれに婿が通ったとしても、邸内における「対の屋」などの建物でそれぞれの居住空間が成り立ったし、またそれぞれの娘夫婦に仕える使用人(女房)も抱えることができた。父親の政治上の立場に伴う経済力が、それらを可能としたのである。
しかし、中下流階層の大半の貴族は、経済的に言えば、せいぜい一人の娘に婿を迎えることがやっとであった。しかも、その場合は、その娘が親の資産の相続権を所有していることが条件でもあった。このことについては、『源氏物語』「東屋」巻での浮舟の破談話が詳細に物語っていよう。浮舟の母が婿候補とした左近の少将は、浮舟が、母の再婚相手である常陸の介の実子ではないことを知り、実子の妹と婚姻したのがそうである。このことにより、浮舟の人生が極めて厳しい局面を迎えたのは言うまでもあるまい。
この浮舟の例が示すように、正規の婚姻関係である「婿取り婚」(通ひ婚)が難しい場合、平安朝の中下流貴族の女たちの現実は厳しかった。そういった現実の厳しさをリアルに語るのが、『伊勢物語』のいくつかの章段なのであって、60段、62段に見られるような女の人生の厳しさは、その現実について、作者がリアルに取り上げたものに過ぎない。そういう意味では、『伊勢物語』は、当時流行していた消閑の具としての「物語」の領域から、大きく逸脱している。
2025.8.23 河地修
一覧へ